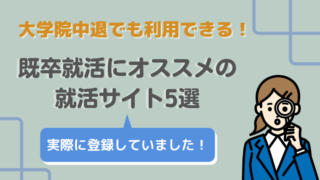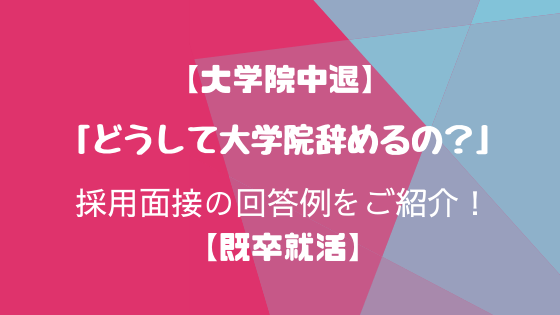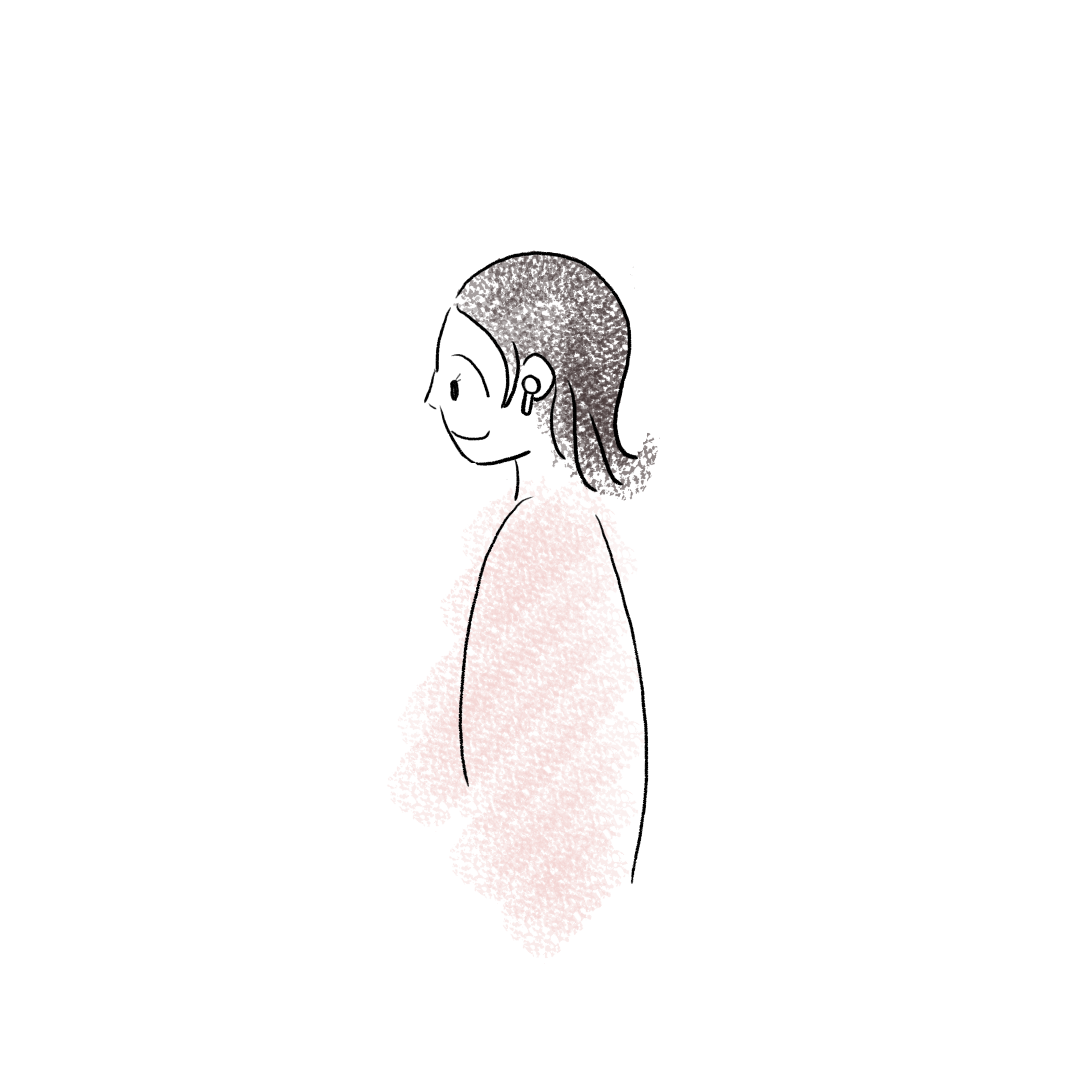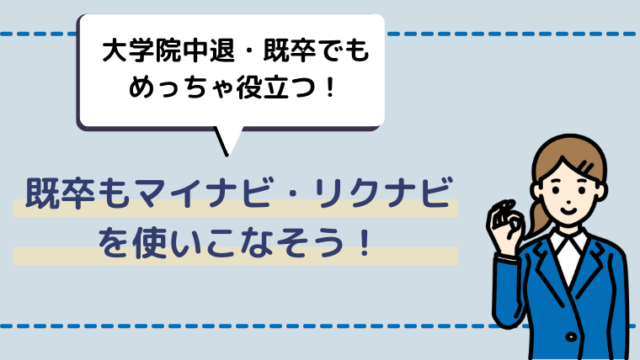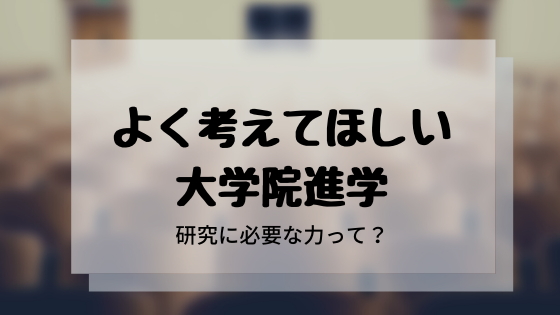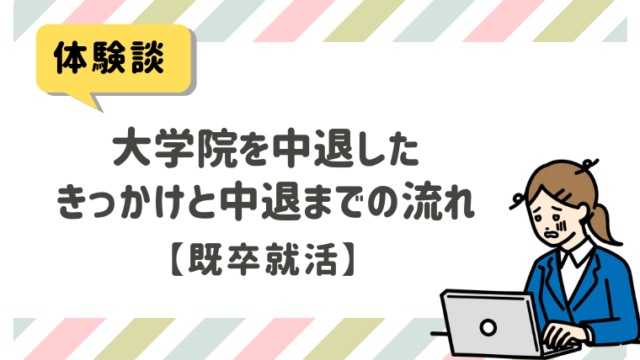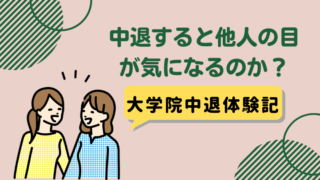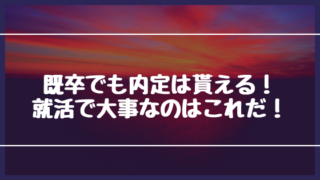私は大学院M1で既卒として就活を行い、内定を得てから大学院を中退しました。
大学院を中退する前提(あるいは中退後)で就職活動をする場合、面接でほぼ確実に聞かれるのが「なぜ大学院を中退したのか」という質問です。
中退という経歴そのものよりも、その理由をどう説明するかによって、面接官の評価は大きく変わります。実際、答え方次第では不利になることもあれば、納得感のある前向きな判断として受け取られることもあります。
この記事では、大学院を中退した人が就活の面接で理由を聞かれたときに、どのように答えればよいのかについて、具体的な考え方と回答例を紹介します。
「大学院中退者は就活で不利なのか」「面接でどう説明すればいいのか」と悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
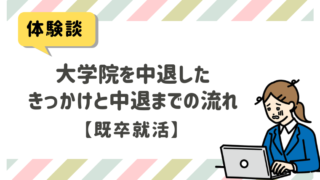
大学院を中退する理由の回答例3パターン【実体験】
面接で「なぜ大学院を辞めてまで就職するのか?」と聞かれた時用に、私はいくつか回答のパターンを用意していました。ここでは、私が実際に使った3つの理由を紹介します。
状況や志望職種にあわせて使い分けましょう。
パターン1:「より社会に貢献していきたくなった」
大学院での研究は、いわゆる基礎研究が多く、社会に貢献する形になるまでには長い時間がかかることが多いです。成果が目に見える形で現れるのは、ずっとずっと先になります。私が研究していた分野も、実用化までには十年以上かかるなと感じていました。
一方で、企業で働くと、社会や人々の生活により直接的に関わることができると気づきました。そこで面接では、
「研究を続ける中で、より社会に近い場で、人々に貢献していきたいと考えるようになりました」
と答えていました。
パターン1を使うときのポイントと注意点
- 「より社会に近い」という言葉を必ず入れること
これが抜けると、「大学での研究は社会の役に立たない」と否定しているようにとられてしまう可能性があります。
- 研究職志望の方には不向き
研究職や開発職を目指す場合、この回答は矛盾しているととらえられるので避けたほうが無難です。逆に、営業職や接客業など、社会と直に関わる仕事を目指す人には相性の良い表現です。
パターン2:「研究を通じて、本当にしたいことに気づいた」
私は毎日研究室で細胞を使った研究に取り組んでいました。当初は、「将来もこの道で生きていくのだろう」となんとなく考えていましたが、実際に研究を続ける中で、「これは自分には向いていない、仕事として続けたいことではない」とはっきり気が付きました。
就活の準備を進める中で、さらに自分のやりたいことが明確になり、「少しでも早くその道で挑戦したい」と感じました。そこで面接では、
「研究を続けるうちに、自分が本当にしたいことが分かりました。少しでも早くそれを実現するため、内定を得たタイミングで大学院を辞める決断をしました。」
と伝えていました。所属している研究室の分野と、受けている企業の分野が大きく異なる場合に使いやすい文章です。
パターン2を使うときのポイントと注意点
- 研究と受けている企業の分野が大きく異なるほど有効
もし、今の研究と同じ分野の企業、職種を受けようとしているならば、「大学院を続けていてもその道には進めますよね?」と問い返される可能性が高いです。そのため、パターン2は、分野を大きく方向転換するときに使うのが効果的でしょう。
- 方向転換の理由を前向きに伝える
「研究が嫌になった」というとネガティブな印象を持たれてしまうので、「これまでの経験を通じてやりたいことを見つけた」と前向きに言い換えることで、面接官が受ける印象が良くなります。
パターン3:「この業界は”今”大きく変化している。そのタイミングを経験したい」
私が最も効果的だと感じた答え方が、この「タイミング」を強調する方法です。
就活を進める中で、たまたま私の志望業界に大きな変化が起きていることを知りました。会社説明の際にも、「今年は〇〇のために大きく環境が変わる」といった話も聞けていたので、「このタイミングを経験できるのは今年入社する人だけだ」と気づき、そこを中退理由にすることにしました。
面接では、以下のように答えていました。
「今年、この業界では〇〇といった変化が起こります。その変化を経験できるのは今だけだと考え、内定を得た時点で大学院を辞める決断をしました。」
入社直後の経験を使って長く働きたいという姿勢を見せられること、業界研究、企業研究がしっかり行えていることを伝えられるという点でも、この中退理由は使いやすいです。
パターン3を使うときのポイントと注意点
- 業界研究、企業研究が前提
「変化している」と言う以上、事実をしっかりと調べておかないと使えません。
- 大げさに言いすぎない
小さな変化を取り上げても構いませんが、あまりにも誇張するのは禁物。例えば、
・営業成績がものすごく上がっている(落ちている)
・国の制度変更で、業界ルールが変わる
・主力製品のヒット、新しい市場への参入で事業体制が変わる
といった事例があると、説得力のある中退理由になります。
大学院中退理由のNG例と注意点|面接で避けるべき答え方
NG例1:人間関係に原因を押し付ける
「教授と合わなかった」「研究室の雰囲気が悪かった」といった理由は、面接官から「環境が合わないとすぐに辞める人なのでは?」と受け取られる可能性が高いです。
NG例2:研究や大学院そのものを否定する
「研究がつまらなかった」「意味を感じられなかった」という学問や研究を否定する発言は、知的好奇心や忍耐力がないと判断されがちです。
NG例3:あいまいな理由でごまかす
「いろいろあって」「なんとなく…」といってはぐらかすと、後ろめたい理由があるのかと勘繰られ、信頼できないととらえられてしまいます。
回答は組み合わせて使ってもよい

実際の面接では、パターン1~3の回答例を使ったとしても、1つの回答だけで終わることはありません。そのため、質問に対してまずパターン1で答え、さらに掘り下げられたらパターン3を使って補足する、というように組み合わせて使うのがよいでしょう。私は実際に、内定を貰った会社の面接官と以下のようなやりとりをしました。
面接官「なぜ大学院を辞めるんですか?」
私「より社会に近い場で貢献したいと考えました(パターン1)」
面接官「でもそれは大学院を修了してからでも可能ですよね?」
私「今年、この業界では〇〇が大きく変わります。その経験は、このタイミングで就職しなければ経験できないので、中退をしてでも入社したいと考えました。(パターン3)」
このように、複数の理由をバランスよく使うと説得力が増します。
まとめ|前向きな選択であることを伝えきることが大事
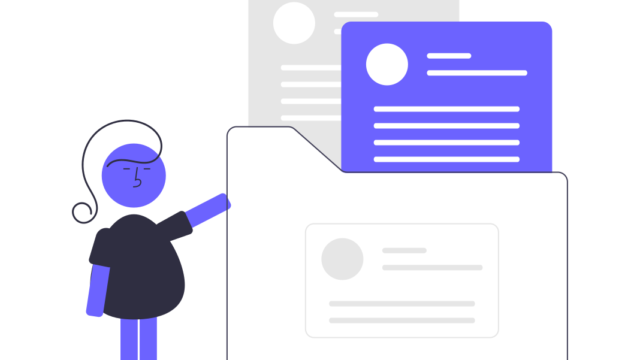
大学院の中退理由を面接で伝えるときに大切なのは、「ネガティブな印象を与えないこと」です。
- 「逃げた」わけではなく進路を見つめ直した
- 「投げ出した」わけではなく前向きに決断した
といったように、表現を工夫すれば、大学院の中退もキャリアを前向きに切り開く選択肢であることを伝えることができます。
ただし、上記のパターン1~3を使って説明をしても、中退に対してネガティブな印象をもっている面接官からはさらに問い詰められることもあります。そのようなときは、無理に明るく振舞うのではなく、
「大学(院)選びは自分の甘さから人の意見に流されて失敗してしまったが、今回はしっかり自分で考えて決めたことなので、後悔することはないはずです」
と、大学院進学を失敗したものと認めた上で、同じ失敗を繰り返さない、と話をするのも効果的です。「今は主体的に選んでいる」と示すことで、素直さと成長意欲を伝えることができます。
いくつかの回答例を紹介しましたが、最も説得力があるのは、自分の体験や将来像に基づいたオリジナルの答えです。この記事を参考にしつつ、自分なりの言葉に整理してみてください。
面接全体の注意事項については、既卒就活で内定を得た私の体験談|ES・自己PR・面接で意識したことでも紹介しています。あわせてご覧ください。
中退理由を考えるのが難しいときは
自分一人で理由を組み立てることが難しいと感じる場合には、既卒専門の就活エージェントを利用するのも有効です。同じように就活に苦労した経験のあるアドバイザーが、プロの視点で中退理由の伝え方や自己PRの整理を手伝ってくれるので、短期間で仕上げやすくなります。
私のお勧めはUZUZ既卒![]() です。
です。
詳しくは以下の記事でまとめていますので、参考にしてみてください。